事例紹介
10億円未満の会社は、
正論だけじゃうまくいかない。
社会の規範やルールを守りつつ、
御社の良さも活かしつつ、次のステップに進む。
Team Coが得意なことです。
事例①:社員の賞与、どのくらいが妥当?
相談事項
「個人事業主として5年、法人化して5年。勢いとノリでやってきた。売上が増えてきたので、一人採用した。されに、もう一人採用した。利益も上がってきたので、賞与もあげたい。でもどのくらいの額が妥当かわからない。税金も払わなきゃいけないし、あれ、思ったより残らなかったな、ということもあるので心配です…」
取り組んだこと:売上と利益、会社の数字を見える化
「経営者が『このくらい売上、利益をあげると、このくらい残っていくんだな』と具体的にわかるように見える化しましょう。そこから、インセンティブ・賞与を決定。売上・利益がこのくらいなら、このくらいもらえるんだ、と社員がわかるように。がんばりと報酬が連動するので、社員の目標意識が高まります。売上が上がりやすい仕組み・制度にすることが重要です。
結果:売上前年比254%に
売上1億1000万円が、翌年2億8000万円に大幅アップ。経常利益3000万円は、5000万円に。社員の給与も1名あたり1200万から2000万円にアップ。
ココがよかったポイント:経費を細かく割り出した
事業はB to CのEコマース。OEMとして外部委託で製造してもらったものを販売するモデルであるため、1個販売するにつき、さまざまな諸経費がかかる。製造原価はもちろんのこと、送料、箱、梱包、広告費など、どのくらいの費用が発生するのか細かく把握。その上で、売上目標をはじめとする計画をつくった。
事例②:赤字事業、いつまで続けていいの?
相談事項
「アパレル企業です。メンズ部門は好調なのですが、レディース部門が赤字続き。しかしながら、思い入れがあるのでやめるという判断ができません。自分たちでイチから立ち上げた部門でもあるし、立ち上げたこと自体が無駄だったんじゃないか、挑戦しない方が良かったんじゃないか、というネガティブな雰囲気になってしまうことも懸念している。」
取り組んだこと:数字を整理する、数字の裏付けをつくる
「思い入れのある事業は、撤退しにくいものです。しかし、だからといって感情論で考えても解決しません。売上・利益などの数字を細かく整理し、売上・利益のボーダーを設定しましょう。赤字部門は黒字部門の利益を削ってしまうことにもなります。一番避けたいのは、黒字部門も苦しくなり共倒れしてしまうこと。そこで、売上・利益の目標数字を設定。このラインを下回った場合は撤退するという共通認識をつくりましょう。」
事例③:10億超えたい!
相談事項
「売上7.3億。10億超えたい。目標数字に根拠はない。コロナ禍で一時数字は落ちたものの、昨今は回復傾向にあるので、頑張りたい。」
取り組んだこと:事業分析、数字の根拠をつくる
「何をどうやったら10億に到達できるのか。事業分析からスタートしましょう。これまでは取引先別の目標数字を設定していたが、ここに「一人あたり売上」という基準を新設定。新卒1年目から年次別で一人あたりいくら稼いでいるのかというデータを算出。ベテランになると管理職も兼ねているケースもある。離職率もある。これらの要素も加味して目標数字を数値化。そこから必要な採用人数も割り出し、営業部門だけでなく、人事部門も巻き込み売上を上げる体制を構築しましょう。」
結果:売上9.6億まで到達。来季は12億を目指す
達成できなかったが、惜しい結果に。10億のその先も目指そうというポジティブな雰囲気が生まれた。また、マネージャーが離職率に目を配るようになったという良い変化も。人事部は採用人数という明確な目標ができたため、採用活動の熱もあがっている。
ここがポイント:数字の持つ意味をしっかりインプット
「あの人はいい案件持っているからラッキーだよね」「自分はチャレンジ案件やってるから、未達でもいいよね」など、言い訳や曖昧な認識があると、目標へのモチベーションを下がってしまう。言い訳を作らないように、数字の持つ意味、その前提を全社員に共有した。経営トップ、役員、マネージャー陣。現場の社員に伝わるように設計・共有することが重要。
事例④:やったほうがいいことはわかっているけれど…
相談事項
「やるべきことがいろいろあるが、どこから手をつけたらいいかわからない。社員のモチベーションをあげたほうがいい。業務の効率化をはかったほうがいい。社員の残業を減らしたほうがいい。どれもやったほうがいいことはわかっているけれど…」
取り組んだこと:目標の整理と共有
「時間もお金も有限。手あたり次第全部やるのではなく、大きな目標・戦略のところから順番に整理していく必要があります。会社として達成したい目標を整理し、戦略を決めましょう。そして実行の仕組み、誰が何をやるべきなのか部門長クラスに落とし込みましょう。そこから各計画に落としていき、やるべきことの優先順位がつけられるようにしましょう。」
ここがポイント:社員に伝わる共有
現場の社員に降りてきた目標は、プロセスがわからないとただのノルマに見えてしまう。会社の状況を把握して、部門や自分のやるべきことが連携するからこそ、数字の意味を理解できる。健康診断の数値と同様。「この数値だから、健康ですよ」と裏付けも伝えることで数字への理解が深まる。
ここがポイント:使われない計画は意味がない、使いたくなる計画に
使われない計画を作っても、それはただのシミュレーション。どう落とし込んでいくかが大事。ITシステムなども同様だが、使われないと意味がない。だから、落としこみ方にこだわる。Team Coの目的はコンサルすることではない、お客様の会社を成長させること。これだけは絶対にブレない。
事例⑤:やりたいことがある。勢いでチャレンジしてもいいですか?
相談事項
「根拠はないが、この事業にチャレンジしてみたい。勢いだけじゃだめですか?」
取り組んだこと:挑戦する際のルールと線引きをつくる
「社長がやりたいことは、やるべきだと考えます。しかし、手離しに何でもやっていいというわけではない。会社が傾くような事態は避けなくてはいけない。うまくいかなかったとしても、ここまでだったら持ちこたえられる。ダメージは大きくない。線引きをしっかりすること。そうすることで、新しいことにも思いっきりアクセルを踏むことができます。」
ここがポイント
以前はこのような相談は、税理士や銀行が相談にいくのが一般的だった。しかし、銀行はお金を貸すことがメイン、税理士は処理することがメイン。やってもいいですよ、ダメですよ、という意見は感覚的で根拠に乏しい。中立的な立場で一緒に考えてくれる存在はなかなかいない。勢いは大事、やりたい気持ちも大事。だからこそ、絶対に失敗してほしくない。私たちが専門的にジャッジして、しっかり成功と失敗の境界線をお見せします。
事例⑥:3億の会社が10億を目指すのが現実的?
相談事項
「飲食店です。今3億。10億いきたい。根拠はありません。」
取り組んだこと:10億届くんじゃないか?と期待されるような事実を作る
「ムーブメントの力を論理的に見せてあげることが大事。3億の会社が10億達成したい。確信がないとなかなか広がらない。10億いけるのでは?と思えるような事実を作る。一般的には店舗数を増やせば売上は上げる。しかし、コストもマンパワーもかかる。そこで、まずはコストをかけずに、回転率を上げて売上を上げる、という作戦で始動しはじめましょう。」
結果:回転率アップ、売上アップ、社内のムードもアップ
中間目標に掲げた、回転率アップ達成。実際に売上もあがり、社内のムードも一変。10億への階段をのぼりはじめることができた。頑張ればいけるかも、というムーブメントを醸成することは何よりも大事。
事例⑦:幹部が育たないのですが…
相談事項
「長年頑張ってきたのに、期待していた幹部候補が離れていってしまった。現状、幹部が育っていません…」
取り組んだこと
「幹部は組織の柱。何があっても崩れない体制のための要です。タイミングを見て、柱を社長から幹部に移行していきたいところです。組織拡大の局面で不可欠なのは仕組み化ですが、仕組みだけで固めてしまうのも考えもの。というのは、「仕組みさえあれば人は誰でもいいの?」と思われてしまう。今は仕組み9割、泥臭さ1割でいきましょう。“あなたでなければならない理由”を社員にしっかり伝えること。組織にとっても、ここはこの人でなければ!幹部にとっても、ここは私でなければ!の両思い理論で強い幹部を育成しましょう」
結果
幹部が育っていないと思われていたが、売上アッププロジェクトを通して、実際には育っていたことが判明。実際に事業が良い方向に向かったことで、全社に自信が。「この人がここにいたから」という唯一無二のドラマが成長を加速させた。社長が現場を完全に離れても、社長がそこにいるかのような組織を、幹部たちがみずから面白がりながらつくりつづけてくれる雰囲気ができてきた。
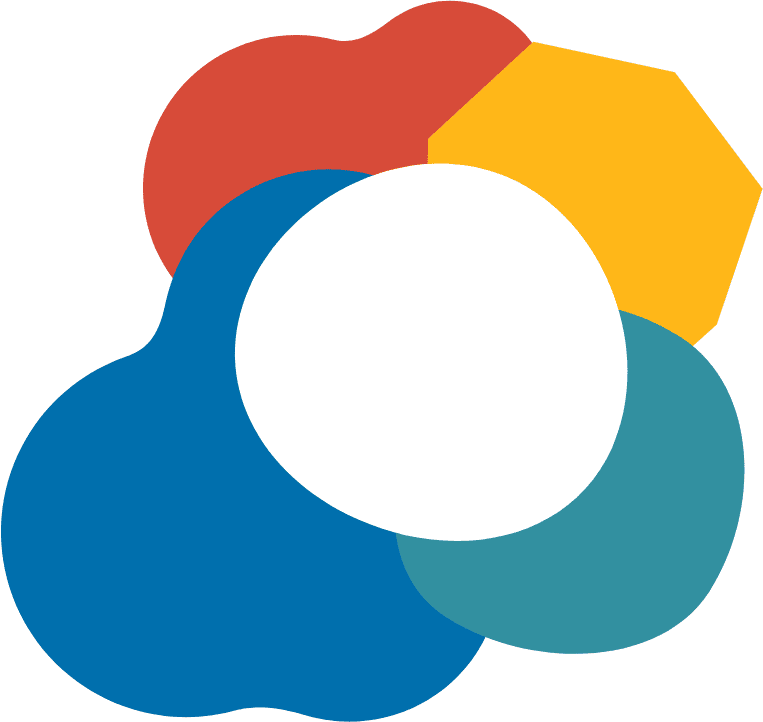
CONTACT
メルマガ申し込みはこちらから
