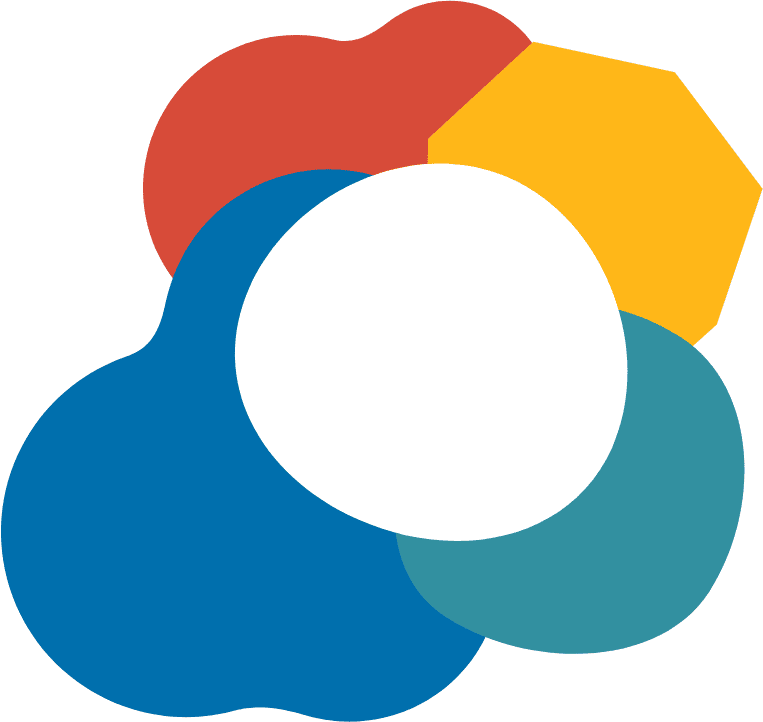インセンティブの効果の最大化
こんにちは!
Team Co株式会社の戦略コンサルタントの榑松 貴です。
このブログは
「年商数億を数十億に成長させたい経営者の皆様へ
数億特有の経営課題を解決するポイントを、お届けしています」
【今日のテーマ】
インセンティブの効果の最大化
数億企業によくある話ですが、
たくさんの会社が、
目標設定をしています。
それは
売上目標かもしれませんし、
利益目標かもしれません。
視点を変えて、
全体の目標かもしれませんし、
個人の目標かもしれません。
いずれにせよ、
「今年1年、
この目標に向かって頑張ろう!」と。
そして1年間
みんなで頑張って、
なんとか目標を
達成することができた。
利益も出た。
その利益は
新たな人の採用や
新規事業のリサーチなど
次の投資に回したり、
もしくは借入の返済に
充てられていく。
だけど
社員も頑張ってくれた。
彼らにも還元したい。
来期はもっと頑張ってほしい。
そのモチベーションにもしてほしい。
ということで、
インセンティブ(決算賞与)を
支給している会社も多いです。
ひとりひとりの
この1年の頑張りを
思い出しながら
それぞれの金額を決める。
喜んでくれるかな、とか
お礼を言われたら
「また来年も頼むよ!」
こんな言葉をかけようかな、とか
そんな想像をする。
そしていざ、社員に
目標に対し結果が
どうだったかを共有する。
そして
「今回はみんな頑張ってくれたから、
インセンティブを出します!」と発表し、
ひとりひとりに給与明細を渡す。
…あれ?
確かに喜んではくれてるけど、
思ったほどの反応じゃない。
こういう話、結構聞きます。
なぜでしょうか。
金額が小さかった?
労いの言葉が足りない?
最近の若い世代は
お金があまり
モチベーションにならない?
社長との信頼関係?
私たちからすれば、
すべてNoです。
インセンティブが
モチベーションにつながらないのは、
金額が小さいのではなく、
労いの言葉が足りないのでもなく、
制度設計に問題がある場合がほとんどです。
上記の例でいえば、
制度が曖昧でした。
具体的には、社員目線に立ったとき、
利益に対して、どのようなプロセスで
金額が決定されたのかが
わからないことに問題があります。
目標を100%達成したらいくら?という基準はあっても、
105%なら?110%なら?
達成度合いに応じた報酬額は、曖昧な会社が多いです。
また、
インセンティブの金額が決算日までわからない
決算日がきてもわからないのも問題です。
そうなると、社長の気分次第で金額が
決まると思う人さえ出てきてしまいます。
これでは
モチベーションにならないどころか、
「あの人は社長に気に入られているから
たくさんもらってる」など、
思わぬ不信を生んだりします。
だからインセンティブは、
明確なロジックで決定され、
100%達成したらいくら、
110%達成したらいくらかがわかる。
(=社員が自分で計算できる)
しかもみんなが納得いくロジックで。
さらにはその金額が
期首時点でわかる。
そうやって設計すると、
見事に業績に寄与する仕組みになります。
さらには、財務的には
どの程度まで支給できるのか、
税務的にはいくら支給するのが妥当なのか。
せっかくインセンティブを入れるなら、
業績につながる、
社員の満足度につながる、
その効果を最大化した仕組みにしたいですね。